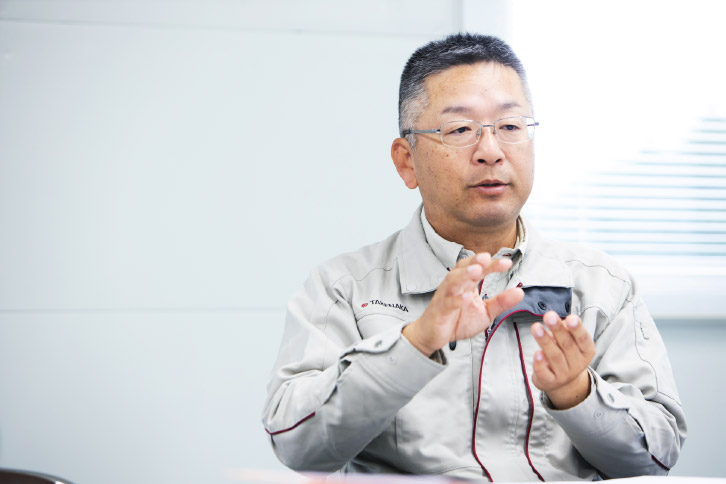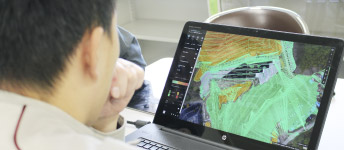住民と思いを一つにする
小さな町は大きな不安に包まれていた。廃棄物の焼却灰、不燃物を埋め立てていた処分場の遮水シートが破損して有害物質が流れ出たためか、地下水からカドミウムが検出されたのだ。地元の湯河原町と真鶴町は約1年がかりで埋立物を搬出。処分施設の再整備工事を行うことになった。2015年、その工事を受注したのが竹中土木。所長として現場に赴くことになったのが、茂呂達明だった。「営業から関わり、工事も自ら赴いて行うことになった。受注・詳細設計・工事と続けて担当するケースは珍しいことで、その点でもやりがいのある仕事だった」(茂呂)。当然のことながら町民の家庭から毎日ゴミは出てくる。処分施設を再整備するとは、その期間中、ゴミの行き場がなくなるということだ。やむなく他の自治体にゴミ処理を依頼するものの、1日も早い竣工が望まれるのは当然である。地域のため、住民のためにという思いが茂呂たち関係者に共通の思いとなったのは、自然なことだった。『みんなの町をいつまでも美しく』。そんなスローガンが現場に掲げられたのもそのためだ。「土木工事でこうしたスローガンを大書して掲げることは珍しい。我々の思いを伝えることで、町民の皆さんとも心を一つにしたかった」と、茂呂は振り返る。