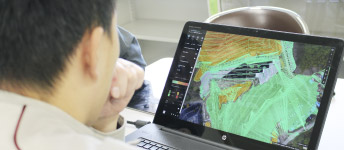それは工期との戦いだった
戦後日本の経済成長を支えてきた東名高速道路。その輸送量は限界に達し、新たな大動脈道路として建設が始まったのが、第二東名高速道路(新東名)だった。小國智一郎が現場所長を命じられたのは、神奈川県秦野市の葛葉川橋下部工工事。難工事と目された現場であったが、小國の胸にあったのは「自分がやるしかない」という、道路や鉄道などの経験豊富なベテランらしい自負だった。
難工事との懸念はすぐに現実のものとなる。埋蔵文化財の調査だ。土偶や剣などが見つかると工事はストップ。遺跡調査が何層にもわたる地層を掘り進んで、調査を終えるのを待たなくてはならない。所長である小國は、そのつど、資材や重機の移動、作業者の調整などに追われた。こうした埋蔵文化財の調査は数ヵ所に及び、ただでさえ余裕のなかった工期はさらにシビアなものになっていったのである。
だが工期の遅れを取り戻すため、小國は“秘策”を仕掛けた。通常は現地で組み立てるコンクリート型枠や足場を事前に組み立てておき、必要な時にすぐさま重機で据え付けるという方法だ。長い現場経験を活かし、工期の遅れをカバーしていったのである。